検証 国家戦略なき日本 (新潮文庫)
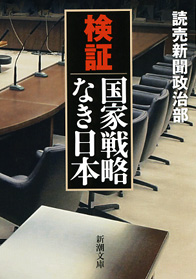
2006/11/22に発売された同名の単行本が文庫化されたものだ。従って内容は2006年当時のものだが、各章の最後に[追記]があり、その後の状況が説明してある。非常に簡単な説明だが好感を感じた。
「はじめに」を読むと、なぜ政治部記者が畑違いの科学技術に関して取材を始め、このような本としてまとめたのかということが熱く語られている。
科学技術、海洋開発、天然資源、安全保障、基礎学力に分けて説明されているが、全体に共通することは、
・国益ではなく省益しか考えない官僚(縦割り省庁の弊害)
・科学技術のことはわからない財務官僚が予算を決めている
・科学技術を理解していない政治家が判断している
と思われ、そういう意味では政治部記者がこの問題を取り上げるのはもっともなことだと感じた。
この中では縦割り省庁の体制にどっぷりと漬かった省益優先、事なかれ主義、責任転嫁の官僚の問題が一番大きそうである。
また、国家戦略とは他国に対して戦略に基づき働きかけ納得させる必要があると思われ、外交能力が非常に重要だと再認識した。
いずれの章でも中国の台頭に触れられており、そのしたたかさに改めて脅威を覚えた。おそらく日本の政治や外交にしたたかさは求めにくいと思われるため、中国などの追い上げに対抗できるような確固たる科学技術の確立とそのための戦略が必要だと感じた。
http://www.shinchosha.co.jp/book/136771/
【内容情報】(新潮社HPより)
国家危機の実像を今こそ直視せよ。安全保障、資源確保、科学政策......、次の総理、必読!
この国の危機の本質は、その針路さえ決めずにいる戦略不在にある──。無資源国でありながら資源確保に遅れをとり、安全大国はもはや幻想となり、科学立国を標榜しながら政策はぐらつき、知財の基盤もゆらいで人材が流出して行く......。国家戦略という視点から、世界の中の日本を多面的に取材した驚愕のレポート。未来に希望を見出だせるのか。今こそ現状を直視しなければならない。
【目次】(新潮社HPより)
はじめに
第1章 科学技術立国の危機
海亀派が牽引する「創新」/宇宙開発も外交手段/2年で陥落した最速スパコンの座/崩れる先端技術の足元/低調な日本のES細胞論議/ゲノム敗北から何を学んだか/ゲノム創薬競争に勝てるか/先行された分子イメージング/気象観測「空白」の危機/ぐらつく国家の意思/影を落とす軍事アレルギー/国政に必要な科学的知見
第2章 漂流する海洋国家
竹島近海での衝突/韓国の周到な海底地名戦略/出遅れた海洋政策/海洋調査、30年の空白/シンプン号事件の悪しき決着/好漁場はなぜ奪われたのか/EEZは「青い国土」/世界の潮流を読めない国/『海猿』への脚光は本物か/外国人船員頼みの海上輸送/" 座礁"寸前の船員教育/LNG船の安全は誰が守るのか/中・韓に敗北した港湾競争/国益無視の港湾行政/国際管理されるマグロ漁/「巨大魚食国」中国の台頭/一国では守れない海の恵み
第3章 自覚なき無資源国
資源を爆食する国/ショッキングな二通りの未来図/中国に牛耳られるレアメタル供給/過熱する資源外交/マラッカ海峡の海賊/思惑絡むシーレーン防衛/脚光浴びる海底資源/沖ノ鳥島が注目される理由/既成事実化される東シナ海開発/省エネ技術を対中戦略に/世界の流れは原子力回帰/政策転換を狙った怪文書/根拠なき国策への"拒否権"/再処理施設は日本の特権/しのぎを削る燃料電池開発
第4章 安全大国の幻想
20年不在のP4施設/「日本は生物テロ容認の国」/心もとない感染症研究の現状/必要な「宝」を生かすネットワーク/生かせぬ最新の地震被害予測/外圧で動いた原発防護策/手つかずの内部脅威対策/不安残る港湾テロ対策/監視カメラ活用は設置者任せ/情報セキュリティーへの低い意識/首相に伝えられなかった情報/情報戦争の最前線/軍事アレルギーの壁
第5章 揺らぐ知力の基盤
覗かれていた特許情報/偽物が本物を駆逐する/知的人材を求めての中国進出/進まない大学の自己改革/外国人研究者が近づけない「知の鎖国」/一貫性欠く対留学生政策/海外誌投稿が招く研究成果流出/国家レベルの標準化戦略/「匠の技」を狙うアジア各国/酷使される「川上」産業/「メイド・イン・ジャパン」の危機/人材は国力のかなめ
おわりに
この国に潜む「禍機」の再検証――文庫版あとがきにかえて――
解説 小林良彰
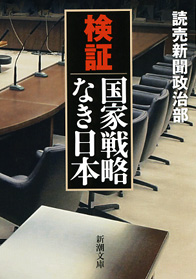
2006/11/22に発売された同名の単行本が文庫化されたものだ。従って内容は2006年当時のものだが、各章の最後に[追記]があり、その後の状況が説明してある。非常に簡単な説明だが好感を感じた。
「はじめに」を読むと、なぜ政治部記者が畑違いの科学技術に関して取材を始め、このような本としてまとめたのかということが熱く語られている。
科学技術、海洋開発、天然資源、安全保障、基礎学力に分けて説明されているが、全体に共通することは、
・国益ではなく省益しか考えない官僚(縦割り省庁の弊害)
・科学技術のことはわからない財務官僚が予算を決めている
・科学技術を理解していない政治家が判断している
と思われ、そういう意味では政治部記者がこの問題を取り上げるのはもっともなことだと感じた。
この中では縦割り省庁の体制にどっぷりと漬かった省益優先、事なかれ主義、責任転嫁の官僚の問題が一番大きそうである。
また、国家戦略とは他国に対して戦略に基づき働きかけ納得させる必要があると思われ、外交能力が非常に重要だと再認識した。
いずれの章でも中国の台頭に触れられており、そのしたたかさに改めて脅威を覚えた。おそらく日本の政治や外交にしたたかさは求めにくいと思われるため、中国などの追い上げに対抗できるような確固たる科学技術の確立とそのための戦略が必要だと感じた。
http://www.shinchosha.co.jp/book/136771/
【内容情報】(新潮社HPより)
国家危機の実像を今こそ直視せよ。安全保障、資源確保、科学政策......、次の総理、必読!
この国の危機の本質は、その針路さえ決めずにいる戦略不在にある──。無資源国でありながら資源確保に遅れをとり、安全大国はもはや幻想となり、科学立国を標榜しながら政策はぐらつき、知財の基盤もゆらいで人材が流出して行く......。国家戦略という視点から、世界の中の日本を多面的に取材した驚愕のレポート。未来に希望を見出だせるのか。今こそ現状を直視しなければならない。
【目次】(新潮社HPより)
はじめに
第1章 科学技術立国の危機
海亀派が牽引する「創新」/宇宙開発も外交手段/2年で陥落した最速スパコンの座/崩れる先端技術の足元/低調な日本のES細胞論議/ゲノム敗北から何を学んだか/ゲノム創薬競争に勝てるか/先行された分子イメージング/気象観測「空白」の危機/ぐらつく国家の意思/影を落とす軍事アレルギー/国政に必要な科学的知見
第2章 漂流する海洋国家
竹島近海での衝突/韓国の周到な海底地名戦略/出遅れた海洋政策/海洋調査、30年の空白/シンプン号事件の悪しき決着/好漁場はなぜ奪われたのか/EEZは「青い国土」/世界の潮流を読めない国/『海猿』への脚光は本物か/外国人船員頼みの海上輸送/" 座礁"寸前の船員教育/LNG船の安全は誰が守るのか/中・韓に敗北した港湾競争/国益無視の港湾行政/国際管理されるマグロ漁/「巨大魚食国」中国の台頭/一国では守れない海の恵み
第3章 自覚なき無資源国
資源を爆食する国/ショッキングな二通りの未来図/中国に牛耳られるレアメタル供給/過熱する資源外交/マラッカ海峡の海賊/思惑絡むシーレーン防衛/脚光浴びる海底資源/沖ノ鳥島が注目される理由/既成事実化される東シナ海開発/省エネ技術を対中戦略に/世界の流れは原子力回帰/政策転換を狙った怪文書/根拠なき国策への"拒否権"/再処理施設は日本の特権/しのぎを削る燃料電池開発
第4章 安全大国の幻想
20年不在のP4施設/「日本は生物テロ容認の国」/心もとない感染症研究の現状/必要な「宝」を生かすネットワーク/生かせぬ最新の地震被害予測/外圧で動いた原発防護策/手つかずの内部脅威対策/不安残る港湾テロ対策/監視カメラ活用は設置者任せ/情報セキュリティーへの低い意識/首相に伝えられなかった情報/情報戦争の最前線/軍事アレルギーの壁
第5章 揺らぐ知力の基盤
覗かれていた特許情報/偽物が本物を駆逐する/知的人材を求めての中国進出/進まない大学の自己改革/外国人研究者が近づけない「知の鎖国」/一貫性欠く対留学生政策/海外誌投稿が招く研究成果流出/国家レベルの標準化戦略/「匠の技」を狙うアジア各国/酷使される「川上」産業/「メイド・イン・ジャパン」の危機/人材は国力のかなめ
おわりに
この国に潜む「禍機」の再検証――文庫版あとがきにかえて――
解説 小林良彰




